フォーラム概要
SNAPフォーラム 企画:構造システム Hall West
実例に学ぶSNAP活用術:進化し続ける構造解析とエンジニアリングの未来
構造システムの解析ソフト「SNAP」は、発売以来25年以上にわたり、多くの構造技術者の皆様にご利用いただいております。
本フォーラムでは、SNAPの最新機能や活用事例、一貫構造計算ソフトや最適化ツールなどのデータ連携、そして構造解析技術の未来についてご紹介いたします。
特に、実際のプロジェクトにおけるユーザー様の具体的な活用事例を通して、SNAPが設計業務の効率化と品質向上にどのように貢献できるかをご紹介し、皆様の業務に役立つヒントを提供いたします。
-
開会あいさつ
千葉 貴史 株式会社構造システム 代表取締役社長

-
WEST1 |
事例紹介13:10 - 14:00

サブストラクチャ仮動的実験でのSNAPの活用
建築研究所で保有する実大鉄筋コンクリート部材が載荷可能な7軸載荷装置に、2023年度にサブストラクチャ仮動的実験システムを導入しました。
本システムは、汎用解析プログラムSNAPと実験加力制御プログラムを連動し、データを相互利用することで地震時の挙動を再現した載荷が可能となるものです。
特に、地震時に大きな変動軸力が作用する構造部材の破壊メカニズムや損傷過程を明らかにすることが期待されます。
本講演では、建築研究所に導入されたサブストラクチャ仮動的実験システムを活用した検討事例を紹介します。
中村 聡宏 氏 ナカムラ アキヒロ
国立研究開発法人 建築研究所 構造研究グループ 主任研究員
1985年 愛知県生まれ
2011年 日本学術振興会 特別研究員DC2
2012年 名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 終了、博士(工学)
2012年 名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 助教
2016年 国立研究開発法人建築研究所 研究員
2018年 国土交通省住宅局建築指導課 構造認定係長
2019年 国立研究開発法人建築研究所 主任研究員(現職)
-
WEST2 |
事例紹介14:15 - 14:55

大規模スタジアムへのSNAP適用事例紹介
SNAPは一般的な建物への適用事例も多くありますが、スタジアムやアリーナといった空間構造にも活用されています。
本講演では、2024年に開業した長崎スタジアムシティ・スタジアム棟でのSNAPの活用事例を紹介いたします。 スタンドと屋根はそれぞれ異なる解析ソフトで検討されることが多いですが、それらを一体化したフル立体モデルを作成し、時刻歴応答解析を行いました。そのモデル化方法や検討内容について紹介いたします。
瀬戸 純平 氏 セト ジュンペイ
株式会社竹中工務店 空間・構造エンジニアリング本部 特殊構造グループ 主任
1989年 千葉県生まれ
2014年 早稲田大学大学院修了後、竹中工務店入社
2015年 現部署に配属
以降、途中2年間の構造設計へのジョブローテーションを経つつ、主に構造解析によるプロジェクト支援に従事。
主な担当プロジェクトに、有明アリーナ、長崎スタジアムシティ・スタジアム棟、大阪・関西万博大屋根リングの解析支援を担当。
-
WEST3 |
事例紹介15:15 - 15:55
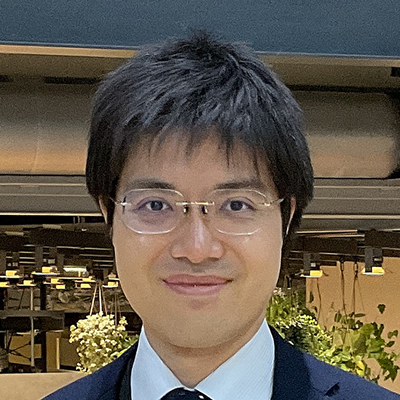
SNAPを連携した構造設計における最適化について
近年、設計案件の大規模化・複雑化が進み、従来の経験則に頼る設計手法では、対応が難しくなってきています。この状況を打破するため、弊社では数年前より、構造設計分野に最適化技術を導入してきました。
当初はデジタルデザインセンター主導で最適化検討を行ってきましたが、2024年からはこのノウハウを社内展開することで、構造設計者自身が最適化検討を主体的に行える体制を整備し、組織全体の設計力向上を図っています。
本講演では、弊社内におけるSNAPを連携した最適化検討の事例、および、設計者自らが最適化を実践できる組織的な取り組みについてご説明いたします。
大江 諭史 氏 オオエ サトシ
清水建設株式会社 設計本部 設計企画室 デジタルデザインセンター デジタルソリューショングループ
1992年 生まれ
2015年 東京大学工学部建築学科卒業
2017年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了
清水建設株式会社に入社 設計本部 構造設計部1部
2020年 同 設計本部 デジタルデザインセンター
現在の主な業務:
・構造最適化をはじめとした案件支援
・構造設計者向けのツール・プログラム等の開発
保有資格:一級建築士、AIジェネラリスト
-
WEST4 |
事例紹介16:10 - 16:50

SNAPのデータ連携の今
現在、構造設計業務の様々な場面において、各種ソフト間のデータ連携の重要性はますます高まっていますが、その自由度はソフトウェアの仕様に大きく依存している状況です。 一方SNAPでは、建物規模や構造種別・形式を問わず、多様な任意形状モデルの解析が可能である強みを持っていますが、その反面、初期データの作成や大幅なモデル更新に時間を要するという課題も挙げられます。
これらの解決の鍵を握るのが、解析モデルの全データをテキストで記述する「s8iファイル」です。この透明性の高いデータ構造が、BIMソフトをはじめ様々なソフトウェアとの柔軟な連携を可能にし、モデリング作業を劇的に自動化・効率化します。
本講演では、具体的な連携事例をもとに、設計業務を加速させるデータ連携の「今」と、その先の可能性について解説します。
多田 聡 タダ サトル
株式会社構造システム 取締役 構造解析部門マネージャー
-
クロージング
多田 聡 株式会社構造システム 取締役 構造解析部門マネージャー
FMフォーラム 企画:FMシステム Hall East
NEXT FM:FM-DXによる新たなステージ
FMの重要性が増しています。FMシステムは、様々なソリューションを活用したFM業務の立案をサポートします。
データセンターのような重要インフラの管理ノウハウも踏まえ、デジタル技術でレジリエンスを強化し、いかなる状況下でも安定した施設運用を実現するためのNEXT FMの形を提案します。
-
開会あいさつ
柴田 英昭 株式会社FMシステム 代表取締役社長

-
EAST1 |
事例紹介13:15 - 13:55

デジタルでつなぐデータセンター構築とFM業務
昨今非常に注目度が高いデータセンター。
NTTDATA では長期にわたり、信頼性の高いデータセンターサービスを提供してきました。
近年のデータセンターの建設需要の増大や、大規模化、設備の複雑化等の外部要因を背景にして、データセンターサービスの核となるファシリティマネジメントの難易度が上がっています。
NTTDATA ではデジタルツイン等の最新技術を活用し、より高度なファシリティマネジメント業務を実現し、より信頼性の高いサービス提供を進めています。
今回、構築から運用をデジタルでつなぐため、いくつもの課題に挑戦し成功に導いた「NTTDATA三鷹ビルEAST(二期棟) BIMを使ったFM業務変革」の取り組みについて紹介します。
遠藤 隆一 氏 エンドウ リュウイチ
株式会社NTTデータ ソリューション事業本部 クラウド&データセンタ事業部 データセンタ統括部
画像認識 AI を活用した検針業務の展開等、FM業務のデジタル化に取り組みFM BIMに関わるPMとして技術検証・PoC を担当
JDCC ファシリティ・スタンダードWG、JFMA BIM―FM研究部会に参加中
-
EAST2 |
事例紹介13:55 - 14:35

BIM-FMのその先へ
~ スマートビル時代におけるデジタルツインの重要性 ~第19回JFMA賞〈技術賞〉を受賞した「ミュージアムタワー京橋BIM活用型FMプラットフォーム構築」の事例を中心にご紹介します。
本事例はEIR(発注者情報要件)に基づき必要情報を整理し、約12万点のFM向けBIMデータを整備。 Webブラウザベースの統合FMプラットフォーム「FM-Integration」上で施設台帳・長期修繕計画・ダッシュボードを統合し、「誰でも使えるBIM」を目指しています。
また、スマートビルが本格化するこれからの時代には、BIMを核としたデジタルツインの重要性が一層高まると考えられます。 本講演では、空間・アセットデータの構造化と生成AIやサービスロボットとの連携の可能性、さらに将来の運用フェーズにおけるデータ利活用についても提案します。
光田 祐介 氏 ミツダ ユウスケ
株式会社日建設計 デジタルソリューション室 アソシエイト
2005年に修士課程を修了後、総合不動産会社に入社し、建築意匠設計に従事。2013年からはBIMの導入・推進とともに、AIやWebサービスを活用した不動産テックの新規事業立ち上げに携わる。
2021年に日建設計へ入社。現在はスマートビルのコンサルティングを主業務とし、BIM-FM・IWMSを基軸にデジタルツイン・XR・ロボットフレンドリーなどの研究開発を通じ、データドリブンな建築の実現を目指している。
日本ファシリティマネジメント協会BIM-FM研究部会、ロボットフレンドリー施設推進機構(物理環境特性TC副TC長)、スマートビルディング共創機構エコシステムWGなど、社外活動にも積極的に参加。
-
EAST3 |
事例紹介14:50 - 15:30

FM-Integrationの最前線
~ 現場からの声 ~自治体では、営繕行政の人手不足及びアナログ作業の根強さにより老朽化した公共施設の修繕計画の未策定が大きな課題になっています。
将来的にも住民サービスの維持と業務効率化を両立させるため、DX導入による改善が急務となっています。
本講演では、江戸川区都市開発部で数多くのデジタル化の整備を行った八武﨑裕也氏が、FM-Integrationを導入し、その後現場で直面する課題とその解決までのアプローチを具体例とともに紹介します。
実践的なノウハウを学べる内容で、公共工事やIT導入に携わる方にとって有益なヒントが得られ、より多くの自治体でFM-Integrationが浸透することが期待されます。
八武﨑 裕也 氏 ヤブサキ ユウヤ
江戸川区 都市開発部施設課 事業調整係 主査
2002年に東京電機大学卒業、その後民間企業に入社し国内問わず多くの電気工事監督に従事。
2012年には、生まれ育った江戸川区役所へ入区し、営繕工事の監督に従事。
2023年には、FM-Integrationを導入。
2024年には、公共工事へDX導入及びペーパーレス化を手がけた功績から東京都建築技術発表会では審査員特別賞を受賞。
現在では、営繕工事の総合調整及び改修計画業務に携わっている。
-
EAST4 |
事例紹介15:30 - 16:10

維持管理BIMの新展開―コンパクトBIMによる実験的アプローチ
~ BIM推進室が提案する、新しい長期修繕計画のかたち ~BIM推進室では、維持管理フェーズにおけるBIM活用の課題を解決するため、「コンパクトBIM」という新たな取り組みを進めています。
本講演では、従来の設計・施工中心のBIMから一歩進み、施設管理者の長期修繕計画立案で迅速に活用できる軽量かつ実用的なBIMモデルの活用手法を紹介します。
具体的には、必要最小限の情報に絞ったモデル設計、既存施設の室形状取得手法、GLOOBEからFM-Integrationへのデータ連携方法などを解説し、BIMモデルの維持管理業務への活用を目指す実験的なアプローチを共有します。
建築とITの融合による新たな価値創出にご期待ください。
脇田 明幸 氏 ワキタ アキヒデ
株式会社奥村組 建築本部 BIM推進室長
1989年京都工芸繊維大学を卒業後、株式会社奥村組に入社、意匠設計業務に従事する。 2015年管理本部情報システム部BIM推進グループ長に就任し、設計・施工におけるBIM活用推進を進めた。 2020年以降はICT統括センターイノベーション部BIM推進室長を務め、国土交通省『BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業』へ参画するなど多方面のBIM活用に努めた。 本年2025年建築本部BIM推進室長に就任し全社の本質的なBIM活用を目指している。
-
EAST5 |
トレンド講演16:10 - 16:55
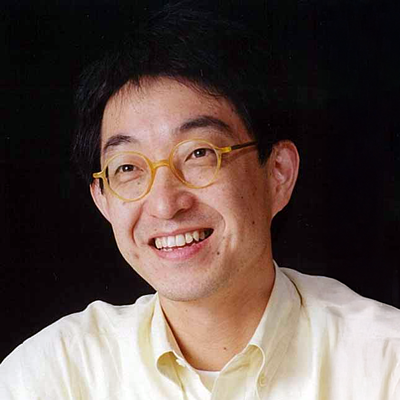
ファシリティマネジメントのためのBIM
BIM(Building Information Modeling)の活用は、建築の設計・施工段階では広がりを見せていますが、FM(ファシリティマネジメント)での活用は未だ十分ではありません。 BIMの情報を活用することでFMの高度化や施設の価値向上が可能だということを考えると、残念な状況といえます。
本講演では、JFMA(日本ファシリティマネジメント協会)のBIM・FM研究部会がまとめた『ファシリティマネジメントのためのBIM要件定義 ― EIR作成ガイド』を題材に、FMに直結するポイントを解説します。 EIR(発注者情報要件)の整理方法、BEP(BIM実行計画書)との関係、LOD/LOI設定の考え方、FM支援システムとのデータ統合などを中心に紹介します。 BIMの情報を施設の運用や維持管理で使える「情報資産」へと発展させるための道筋を示すとともに、ファシリティマネジャーがBIMを活用するために必要な情報を提供します。
猪里 孝司 氏 イザト タカシ
大成建設株式会社 設計本部 設計企画部室長 / JFMA 調査研究委員会 BIM・FM研究部会長
1986年大阪大学大学院修了、大成建設入社。情報システム部門および建築設計部門においてCAD, CGの開発・運用やFMでのBIM活用に従事。現在は設計業務でのICT活用に携わっている。 また、2012年から日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)のBIM・FM研究部会長をつとめ、建物の運用・維持管理段階でのBIMおよび建築のデジタル情報活用に取り組んでいる。
-
クロージング
鑓田 明利 株式会社FMシステム 取締役 システム営業部長
建築フォーラム 企画:建築ピボット Terrace Room
「境界を越える建築家たち」― 組織・ネットワーク・発信力で拓く新しい時代のビジネスモデル ―
本フォーラムでは、これまでの建築設計における慣習や制度の枠にとらわれずに新しい働き方・ビジネスモデルを実践する3名の登壇者が、その事業運営やチームづくり、情報発信のリアルな取り組みを紹介します。
組織の力を最大限に引き出す働き方を重視した組織運営、柔軟な働きかたとネットワークを活かしてプロジェクトを共創するチーム、女性ならではの視点を生かしたSNSでの情報発信など、それぞれの実践から、分野や形態の境界を越えて活動する建築業界の可能性と広がる価値を探ります。
-
開会あいさつ
長谷川 秀武 株式会社建築ピボット 取締役

-
CAD・CGツールがデザインを生み出す
~ 実務における複雑な制約下でデザインをいかに生成し続けるか ~我々は長らく、一握りの才能やセンスに依存して建築のデザインを生み出してきました。
大学教育では依然として手描きや模型づくりが重視されますが、実務の現場では高度なCAD・CGツールを駆使しなければ成立しない時代に突入しています。 現在は、それらのツールを的確に使いこなすことで、複雑で自由度の高いデザインを正確かつスピーディーに生み出すことが可能になっています。
本講演では、Computer-Aided Design (CAD) を単なる補助としてではなく、発想を形に変える主役の道具として活用し、実務においてどのように複雑な建築を実現しているのかをご紹介します。
AIによる設計の自動化(Generative Design)に至る前段階として、建築家の感性とソフトウェアの能力を融合させる実践的なプロセスを共有し、これからの建築デザインにおける可能性を考える機会としたいと思います。
井上 雅宏 氏 イノウエ マサヒロ
株式会社フィールド・デザイン・アーキテクツ一級建築士事務所 代表取締役
これからの時代の設計事務所を確立することを目指しています。
楽しく仕事ができかつ、最先端な環境が、設計者のパフォーマンスを最大限に発揮するはずです。
都心にたくさんの建築を設計し、都市の風景に私たち一人一人がデザインする建築の風を吹き込みます。
1994 早稲田大学建築学科卒業
1996 早稲田大学修士課程修了
1996~1998 株式会社伊東豊雄建築設計事務所
2000~2004 タウン企画設計株式会社
2004~2009 株式会社現代建築研究所
2009~ フィールド・デザイン・アーキテクツ一級建築士事務所 設立
2012~ 株式会社に改組
2021~ 日本建築家協会関東甲信越支部JIA神奈川副代表
2025~ 神奈川県建築会議幹事
-
建築設計者集団を構築するためのネットワークの実践
~ フレキシブルで有事の際にも助け合える、芸能事務所のような設計事務所へ ~当社は、全国各地の建築設計者とネットワークを構築し、案件ごとに最適なチームを編成することで、柔軟かつ高品質な設計業務を実現しています。
本講演では、当社の特色である「多彩なメンバー構成」と「ITツールの活用」を中心に、実際のプロジェクト事例を交えながら、チームによる設計体制とその運用方法をご紹介します。 クラウドツールの導入により、データ共有や情報管理の効率化を図りつつ、遠隔地のメンバーとも円滑に連携する仕組みを構築しています。 当社への参画メンバーも年々増えており、今後は業務のさらなる拡大も見込んで、体制整備にも段階的に取り組んでいます。 まだまだ発展途上ではありますが、建築とITの融合による持続可能な業務モデルの構築を目指す私たちの取り組みに、ご関心をお寄せいただければ幸いです。
廣田 裕基 氏 ヒロタ ユウキ
株式会社あくと総合計画 代表取締役
1987年 埼玉県生まれ
2010年 工学院大学卒業後、設計事務所勤務
2015年 独立
2018年 株式会社あくと総合計画 代表取締役就任
一級建築士。住宅・事務所・商業施設などの設計監理を多数手がける。
また建築設計の視点を生かし、まちづくり・飲食店経営・農業など、多様な取組みを展開している。
としま街づくり推進協会 代表理事
館林商工会議所青年部 観光推進委員会 委員長
関東ブロック商工会議所連合会 スクラム政策提言委員会
東京都建築士会青年委員会
東京都建築士事務所協会港支部
東京都建築士事務所協会青年部
神楽坂商店街振興組合
館林観光協会
-
建築DXの次は“WX”へ
~ Women × SNSが切り拓く建築の人材確保と顧客獲得の次世代戦略 ~建築業界ではDXによる効率化や技術革新が進む一方、人材不足やお客様との関わり方といった“人”の課題は依然として残されています。
その次の変革のカギとして、私は「WX(Women × SNS)」を提唱します。
私が創業した女子建築設計株式会社は、19名の小さな会社ながら、女性が自分らしく力を発揮できる場をつくり、創業から6年間で着実に歩みを重ねてきました。
女性目線のリノベ提案はお客様の共感を生み、契約率は約50%を実現。 さらにSNSでの発信は、集客に留まらず採用にも広がり、新しい仲間とお客様をつなぐ場となっています。
これまで建築業界では女性が活躍できる場は限られてきましたが、次の世代にはもっと可能性を広げたい。 女性だからこそできる“暮らしを変えるリノベ”で、今度は女性から建築業界の未来を描き始めたいと考えています。 小さな会社だからこそ挑める試みを重ね、業界に小さな変化のきっかけを届けたいと思います。
大津 美奈子 氏 オオツ ミナコ
女子建築設計株式会社 代表取締役
一級建築士としてリノベーション業界で30年以上の経験を重ね、大手企業で設計営業を担当。 男性中心の建設業界に課題を感じたことを原点に、2019年に大阪で「女子建築設計株式会社」を設立した。 現在は社員19名規模の建築会社に成長し、大規模リノベーションを専門に女性が活躍できる環境づくりを進めている。
YouTubeやInstagramを通じた情報発信にも取り組み、集客や採用へとつなげている。 近年は建築DXの先に「WX(Women × SNS)」を掲げ、女性の視点から、建築・リノベ業界に新しい形を探りつつ、一歩ずつ進めている。
-
Terrace4 |
事例紹介16:20 - 16:50

プロジェクトを現実空間に可視化する!
~ スマホひとつで簡単にできるARの活用テクニック ~従来のプロジェクト説明や設計レビューでは、図面や模型を通じて「見る」ことが中心でした。 しかし、それだけでは関係者全員に同じイメージを共有するのが難しいという課題があります。
そこで注目されているのが、近年急速に普及してきた AR(拡張現実)技術 です。 ARを活用すれば、スマートフォンやタブレットを通して実寸大の建築や設備を「その場にあるかのように」体験できます。 モバイルアプリ 「DRA AR」 は、高価な機材や専門知識を必要とせず、手持ちのスマートフォンだけで、手軽にこの体験を実現します。
本講演では、実際の活用事例を交えながら「見る」から「体験する」へと変わる新しい形をご紹介します。
岸 航平 キシ コウヘイ
株式会社建築ピボット 開発部門
-
クロージング
千葉 貴史 株式会社建築ピボット 代表取締役社長
ネットワーキング
パーティー Reception Hall
本イベント終了後、17:20からネットワーキングパーティーを開催します。
フォーラムでの学びを深めつつ、業界のキーパーソンや登壇者と直接交流できる貴重な機会です。ビジネスの可能性を広げる場としてご活用ください。
どなた様でもご参加いただけます。
お時間ございましたら、お気軽にお立ち寄りください
SNAPフォーラム 企画:構造システム Hall West
実例に学ぶSNAP活用術:進化し続ける構造解析とエンジニアリングの未来
構造システムの解析ソフト「SNAP」は、発売以来25年以上にわたり、多くの構造技術者の皆様にご利用いただいております。
本フォーラムでは、SNAPの最新機能や活用事例、一貫構造計算ソフトや最適化ツールなどのデータ連携、そして構造解析技術の未来についてご紹介いたします。
特に、実際のプロジェクトにおけるユーザー様の具体的な活用事例を通して、SNAPが設計業務の効率化と品質向上にどのように貢献できるかをご紹介し、皆様の業務に役立つヒントを提供いたします。
-
開会あいさつ
千葉 貴史 株式会社構造システム 代表取締役社長

-
WEST1 |
事例紹介13:10 - 14:00

サブストラクチャ仮動的実験でのSNAPの活用
建築研究所で保有する実大鉄筋コンクリート部材が載荷可能な7軸載荷装置に、2023年度にサブストラクチャ仮動的実験システムを導入しました。
本システムは、汎用解析プログラムSNAPと実験加力制御プログラムを連動し、データを相互利用することで地震時の挙動を再現した載荷が可能となるものです。
特に、地震時に大きな変動軸力が作用する構造部材の破壊メカニズムや損傷過程を明らかにすることが期待されます。
本講演では、建築研究所に導入されたサブストラクチャ仮動的実験システムを活用した検討事例を紹介します。
中村 聡宏 氏 ナカムラ アキヒロ
国立研究開発法人 建築研究所 構造研究グループ 主任研究員
1985年 愛知県生まれ
2011年 日本学術振興会 特別研究員DC2
2012年 名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 終了、博士(工学)
2012年 名古屋大学大学院環境学研究科都市環境学専攻 助教
2016年 国立研究開発法人建築研究所 研究員
2018年 国土交通省住宅局建築指導課 構造認定係長
2019年 国立研究開発法人建築研究所 主任研究員(現職)
-
WEST2 |
事例紹介14:15 - 14:55

大規模スタジアムへのSNAP適用事例紹介
SNAPは一般的な建物への適用事例も多くありますが、スタジアムやアリーナといった空間構造にも活用されています。
本講演では、2024年に開業した長崎スタジアムシティ・スタジアム棟でのSNAPの活用事例を紹介いたします。 スタンドと屋根はそれぞれ異なる解析ソフトで検討されることが多いですが、それらを一体化したフル立体モデルを作成し、時刻歴応答解析を行いました。そのモデル化方法や検討内容について紹介いたします。
瀬戸 純平 氏 セト ジュンペイ
株式会社竹中工務店 空間・構造エンジニアリング本部 特殊構造グループ 主任
1989年 千葉県生まれ
2014年 早稲田大学大学院修了後、竹中工務店入社
2015年 現部署に配属
以降、途中2年間の構造設計へのジョブローテーションを経つつ、主に構造解析によるプロジェクト支援に従事。
主な担当プロジェクトに、有明アリーナ、長崎スタジアムシティ・スタジアム棟、大阪・関西万博大屋根リングの解析支援を担当。
-
WEST3 |
事例紹介15:15 - 15:55
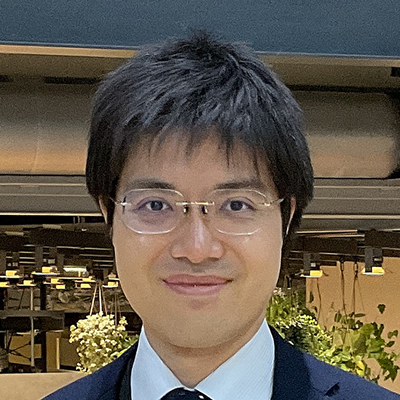
SNAPを連携した構造設計における最適化について
近年、設計案件の大規模化・複雑化が進み、従来の経験則に頼る設計手法では、対応が難しくなってきています。この状況を打破するため、弊社では数年前より、構造設計分野に最適化技術を導入してきました。
当初はデジタルデザインセンター主導で最適化検討を行ってきましたが、2024年からはこのノウハウを社内展開することで、構造設計者自身が最適化検討を主体的に行える体制を整備し、組織全体の設計力向上を図っています。
本講演では、弊社内におけるSNAPを連携した最適化検討の事例、および、設計者自らが最適化を実践できる組織的な取り組みについてご説明いたします。
大江 諭史 氏 オオエ サトシ
清水建設株式会社 設計本部 設計企画室 デジタルデザインセンター デジタルソリューショングループ
1992年 生まれ
2015年 東京大学工学部建築学科卒業
2017年 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了
清水建設株式会社に入社 設計本部 構造設計部1部
2020年 同 設計本部 デジタルデザインセンター
現在の主な業務:
・構造最適化をはじめとした案件支援
・構造設計者向けのツール・プログラム等の開発
保有資格:一級建築士、AIジェネラリスト
-
WEST4 |
事例紹介16:10 - 16:50

SNAPのデータ連携の今
現在、構造設計業務の様々な場面において、各種ソフト間のデータ連携の重要性はますます高まっていますが、その自由度はソフトウェアの仕様に大きく依存している状況です。 一方SNAPでは、建物規模や構造種別・形式を問わず、多様な任意形状モデルの解析が可能である強みを持っていますが、その反面、初期データの作成や大幅なモデル更新に時間を要するという課題も挙げられます。
これらの解決の鍵を握るのが、解析モデルの全データをテキストで記述する「s8iファイル」です。この透明性の高いデータ構造が、BIMソフトをはじめ様々なソフトウェアとの柔軟な連携を可能にし、モデリング作業を劇的に自動化・効率化します。
本講演では、具体的な連携事例をもとに、設計業務を加速させるデータ連携の「今」と、その先の可能性について解説します。
多田 聡 タダ サトル
株式会社構造システム 取締役 構造解析部門マネージャー
-
クロージング
多田 聡 株式会社構造システム 取締役 構造解析部門マネージャー
ネットワーキング
パーティー Reception Hall
本イベント終了後、17:20からネットワーキングパーティーを開催します。
フォーラムでの学びを深めつつ、業界のキーパーソンや登壇者と直接交流できる貴重な機会です。ビジネスの可能性を広げる場としてご活用ください。
どなた様でもご参加いただけます。
お時間ございましたら、お気軽にお立ち寄りください
FMフォーラム 企画:FMシステム Hall East
NEXT FM:FM-DXによる新たなステージ
FMの重要性が増しています。FMシステムは、様々なソリューションを活用したFM業務の立案をサポートします。
データセンターのような重要インフラの管理ノウハウも踏まえ、デジタル技術でレジリエンスを強化し、いかなる状況下でも安定した施設運用を実現するためのNEXT FMの形を提案します。
-
開会あいさつ
柴田 英昭 株式会社FMシステム 代表取締役社長

-
EAST1 |
事例紹介13:15 - 13:55

デジタルでつなぐデータセンター構築とFM業務
昨今非常に注目度が高いデータセンター。
NTTDATA では長期にわたり、信頼性の高いデータセンターサービスを提供してきました。
近年のデータセンターの建設需要の増大や、大規模化、設備の複雑化等の外部要因を背景にして、データセンターサービスの核となるファシリティマネジメントの難易度が上がっています。
NTTDATA ではデジタルツイン等の最新技術を活用し、より高度なファシリティマネジメント業務を実現し、より信頼性の高いサービス提供を進めています。
今回、構築から運用をデジタルでつなぐため、いくつもの課題に挑戦し成功に導いた「NTTDATA三鷹ビルEAST(二期棟) BIMを使ったFM業務変革」の取り組みについて紹介します。
遠藤 隆一 氏 エンドウ リュウイチ
株式会社NTTデータ ソリューション事業本部 クラウド&データセンタ事業部 データセンタ統括部
画像認識 AI を活用した検針業務の展開等、FM業務のデジタル化に取り組みFM BIMに関わるPMとして技術検証・PoC を担当
JDCC ファシリティ・スタンダードWG、JFMA BIM―FM研究部会に参加中
-
EAST2 |
事例紹介13:55 - 14:35

BIM-FMのその先へ
~ スマートビル時代におけるデジタルツインの重要性 ~第19回JFMA賞〈技術賞〉を受賞した「ミュージアムタワー京橋BIM活用型FMプラットフォーム構築」の事例を中心にご紹介します。
本事例はEIR(発注者情報要件)に基づき必要情報を整理し、約12万点のFM向けBIMデータを整備。 Webブラウザベースの統合FMプラットフォーム「FM-Integration」上で施設台帳・長期修繕計画・ダッシュボードを統合し、「誰でも使えるBIM」を目指しています。
また、スマートビルが本格化するこれからの時代には、BIMを核としたデジタルツインの重要性が一層高まると考えられます。 本講演では、空間・アセットデータの構造化と生成AIやサービスロボットとの連携の可能性、さらに将来の運用フェーズにおけるデータ利活用についても提案します。
光田 祐介 氏 ミツダ ユウスケ
株式会社日建設計 デジタルソリューション室 アソシエイト
2005年に修士課程を修了後、総合不動産会社に入社し、建築意匠設計に従事。2013年からはBIMの導入・推進とともに、AIやWebサービスを活用した不動産テックの新規事業立ち上げに携わる。
2021年に日建設計へ入社。現在はスマートビルのコンサルティングを主業務とし、BIM-FM・IWMSを基軸にデジタルツイン・XR・ロボットフレンドリーなどの研究開発を通じ、データドリブンな建築の実現を目指している。
日本ファシリティマネジメント協会BIM-FM研究部会、ロボットフレンドリー施設推進機構(物理環境特性TC副TC長)、スマートビルディング共創機構エコシステムWGなど、社外活動にも積極的に参加。
-
EAST3 |
事例紹介14:50 - 15:30

FM-Integrationの最前線
~ 現場からの声 ~自治体では、営繕行政の人手不足及びアナログ作業の根強さにより老朽化した公共施設の修繕計画の未策定が大きな課題になっています。
将来的にも住民サービスの維持と業務効率化を両立させるため、DX導入による改善が急務となっています。
本講演では、江戸川区都市開発部で数多くのデジタル化の整備を行った八武﨑裕也氏が、FM-Integrationを導入し、その後現場で直面する課題とその解決までのアプローチを具体例とともに紹介します。
実践的なノウハウを学べる内容で、公共工事やIT導入に携わる方にとって有益なヒントが得られ、より多くの自治体でFM-Integrationが浸透することが期待されます。
八武﨑 裕也 氏 ヤブサキ ユウヤ
江戸川区 都市開発部施設課 事業調整係 主査
2002年に東京電機大学卒業、その後民間企業に入社し国内問わず多くの電気工事監督に従事。
2012年には、生まれ育った江戸川区役所へ入区し、営繕工事の監督に従事。
2023年には、FM-Integrationを導入。
2024年には、公共工事へDX導入及びペーパーレス化を手がけた功績から東京都建築技術発表会では審査員特別賞を受賞。
現在では、営繕工事の総合調整及び改修計画業務に携わっている。
-
EAST4 |
事例紹介15:30 - 16:10

維持管理BIMの新展開―コンパクトBIMによる実験的アプローチ
~ BIM推進室が提案する、新しい長期修繕計画のかたち ~BIM推進室では、維持管理フェーズにおけるBIM活用の課題を解決するため、「コンパクトBIM」という新たな取り組みを進めています。
本講演では、従来の設計・施工中心のBIMから一歩進み、施設管理者の長期修繕計画立案で迅速に活用できる軽量かつ実用的なBIMモデルの活用手法を紹介します。
具体的には、必要最小限の情報に絞ったモデル設計、既存施設の室形状取得手法、GLOOBEからFM-Integrationへのデータ連携方法などを解説し、BIMモデルの維持管理業務への活用を目指す実験的なアプローチを共有します。
建築とITの融合による新たな価値創出にご期待ください。
脇田 明幸 氏 ワキタ アキヒデ
株式会社奥村組 建築本部 BIM推進室長
1989年京都工芸繊維大学を卒業後、株式会社奥村組に入社、意匠設計業務に従事する。 2015年管理本部情報システム部BIM推進グループ長に就任し、設計・施工におけるBIM活用推進を進めた。 2020年以降はICT統括センターイノベーション部BIM推進室長を務め、国土交通省『BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業』へ参画するなど多方面のBIM活用に努めた。 本年2025年建築本部BIM推進室長に就任し全社の本質的なBIM活用を目指している。
-
EAST5 |
トレンド講演16:10 - 16:55
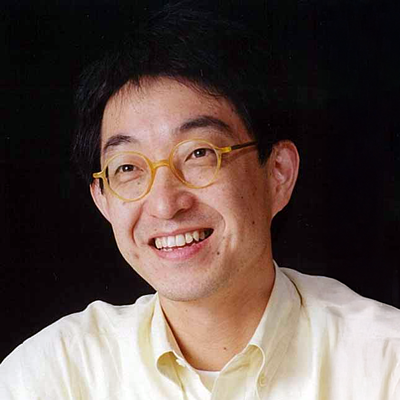
ファシリティマネジメントのためのBIM
BIM(Building Information Modeling)の活用は、建築の設計・施工段階では広がりを見せていますが、FM(ファシリティマネジメント)での活用は未だ十分ではありません。 BIMの情報を活用することでFMの高度化や施設の価値向上が可能だということを考えると、残念な状況といえます。
本講演では、JFMA(日本ファシリティマネジメント協会)のBIM・FM研究部会がまとめた『ファシリティマネジメントのためのBIM要件定義 ― EIR作成ガイド』を題材に、FMに直結するポイントを解説します。 EIR(発注者情報要件)の整理方法、BEP(BIM実行計画書)との関係、LOD/LOI設定の考え方、FM支援システムとのデータ統合などを中心に紹介します。 BIMの情報を施設の運用や維持管理で使える「情報資産」へと発展させるための道筋を示すとともに、ファシリティマネジャーがBIMを活用するために必要な情報を提供します。
猪里 孝司 氏 イザト タカシ
大成建設株式会社 設計本部 設計企画部室長 / JFMA 調査研究委員会 BIM・FM研究部会長
1986年大阪大学大学院修了、大成建設入社。情報システム部門および建築設計部門においてCAD, CGの開発・運用やFMでのBIM活用に従事。現在は設計業務でのICT活用に携わっている。 また、2012年から日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)のBIM・FM研究部会長をつとめ、建物の運用・維持管理段階でのBIMおよび建築のデジタル情報活用に取り組んでいる。
-
クロージング
鑓田 明利 株式会社FMシステム 取締役 システム営業部長
ネットワーキング
パーティー Reception Hall
本イベント終了後、17:20からネットワーキングパーティーを開催します。
フォーラムでの学びを深めつつ、業界のキーパーソンや登壇者と直接交流できる貴重な機会です。ビジネスの可能性を広げる場としてご活用ください。
どなた様でもご参加いただけます。
お時間ございましたら、お気軽にお立ち寄りください
建築フォーラム 企画:建築ピボット Terrace Room
「境界を越える建築家たち」― 組織・ネットワーク・発信力で拓く新しい時代のビジネスモデル ―
本フォーラムでは、これまでの建築設計における慣習や制度の枠にとらわれずに新しい働き方・ビジネスモデルを実践する3名の登壇者が、その事業運営やチームづくり、情報発信のリアルな取り組みを紹介します。
組織の力を最大限に引き出す働き方を重視した組織運営、柔軟な働きかたとネットワークを活かしてプロジェクトを共創するチーム、女性ならではの視点を生かしたSNSでの情報発信など、それぞれの実践から、分野や形態の境界を越えて活動する建築業界の可能性と広がる価値を探ります。
-
開会あいさつ
長谷川 秀武 株式会社建築ピボット 取締役

-
CAD・CGツールがデザインを生み出す
~ 実務における複雑な制約下でデザインをいかに生成し続けるか ~我々は長らく、一握りの才能やセンスに依存して建築のデザインを生み出してきました。
大学教育では依然として手描きや模型づくりが重視されますが、実務の現場では高度なCAD・CGツールを駆使しなければ成立しない時代に突入しています。 現在は、それらのツールを的確に使いこなすことで、複雑で自由度の高いデザインを正確かつスピーディーに生み出すことが可能になっています。
本講演では、Computer-Aided Design (CAD) を単なる補助としてではなく、発想を形に変える主役の道具として活用し、実務においてどのように複雑な建築を実現しているのかをご紹介します。
AIによる設計の自動化(Generative Design)に至る前段階として、建築家の感性とソフトウェアの能力を融合させる実践的なプロセスを共有し、これからの建築デザインにおける可能性を考える機会としたいと思います。
井上 雅宏 氏 イノウエ マサヒロ
株式会社フィールド・デザイン・アーキテクツ一級建築士事務所 代表取締役
これからの時代の設計事務所を確立することを目指しています。
楽しく仕事ができかつ、最先端な環境が、設計者のパフォーマンスを最大限に発揮するはずです。
都心にたくさんの建築を設計し、都市の風景に私たち一人一人がデザインする建築の風を吹き込みます。
1994 早稲田大学建築学科卒業
1996 早稲田大学修士課程修了
1996~1998 株式会社伊東豊雄建築設計事務所
2000~2004 タウン企画設計株式会社
2004~2009 株式会社現代建築研究所
2009~ フィールド・デザイン・アーキテクツ一級建築士事務所 設立
2012~ 株式会社に改組
2021~ 日本建築家協会関東甲信越支部JIA神奈川副代表
2025~ 神奈川県建築会議幹事
-
建築設計者集団を構築するためのネットワークの実践
~ フレキシブルで有事の際にも助け合える、芸能事務所のような設計事務所へ ~当社は、全国各地の建築設計者とネットワークを構築し、案件ごとに最適なチームを編成することで、柔軟かつ高品質な設計業務を実現しています。
本講演では、当社の特色である「多彩なメンバー構成」と「ITツールの活用」を中心に、実際のプロジェクト事例を交えながら、チームによる設計体制とその運用方法をご紹介します。 クラウドツールの導入により、データ共有や情報管理の効率化を図りつつ、遠隔地のメンバーとも円滑に連携する仕組みを構築しています。 当社への参画メンバーも年々増えており、今後は業務のさらなる拡大も見込んで、体制整備にも段階的に取り組んでいます。 まだまだ発展途上ではありますが、建築とITの融合による持続可能な業務モデルの構築を目指す私たちの取り組みに、ご関心をお寄せいただければ幸いです。
廣田 裕基 氏 ヒロタ ユウキ
株式会社あくと総合計画 代表取締役
1987年 埼玉県生まれ
2010年 工学院大学卒業後、設計事務所勤務
2015年 独立
2018年 株式会社あくと総合計画 代表取締役就任
一級建築士。住宅・事務所・商業施設などの設計監理を多数手がける。
また建築設計の視点を生かし、まちづくり・飲食店経営・農業など、多様な取組みを展開している。
としま街づくり推進協会 代表理事
館林商工会議所青年部 観光推進委員会 委員長
関東ブロック商工会議所連合会 スクラム政策提言委員会
東京都建築士会青年委員会
東京都建築士事務所協会港支部
東京都建築士事務所協会青年部
神楽坂商店街振興組合
館林観光協会
-
建築DXの次は“WX”へ
~ Women × SNSが切り拓く建築の人材確保と顧客獲得の次世代戦略 ~建築業界ではDXによる効率化や技術革新が進む一方、人材不足やお客様との関わり方といった“人”の課題は依然として残されています。
その次の変革のカギとして、私は「WX(Women × SNS)」を提唱します。
私が創業した女子建築設計株式会社は、19名の小さな会社ながら、女性が自分らしく力を発揮できる場をつくり、創業から6年間で着実に歩みを重ねてきました。
女性目線のリノベ提案はお客様の共感を生み、契約率は約50%を実現。 さらにSNSでの発信は、集客に留まらず採用にも広がり、新しい仲間とお客様をつなぐ場となっています。
これまで建築業界では女性が活躍できる場は限られてきましたが、次の世代にはもっと可能性を広げたい。 女性だからこそできる“暮らしを変えるリノベ”で、今度は女性から建築業界の未来を描き始めたいと考えています。 小さな会社だからこそ挑める試みを重ね、業界に小さな変化のきっかけを届けたいと思います。
大津 美奈子 氏 オオツ ミナコ
女子建築設計株式会社 代表取締役
一級建築士としてリノベーション業界で30年以上の経験を重ね、大手企業で設計営業を担当。 男性中心の建設業界に課題を感じたことを原点に、2019年に大阪で「女子建築設計株式会社」を設立した。 現在は社員19名規模の建築会社に成長し、大規模リノベーションを専門に女性が活躍できる環境づくりを進めている。
YouTubeやInstagramを通じた情報発信にも取り組み、集客や採用へとつなげている。 近年は建築DXの先に「WX(Women × SNS)」を掲げ、女性の視点から、建築・リノベ業界に新しい形を探りつつ、一歩ずつ進めている。
-
Terrace4 |
事例紹介16:20 - 16:50

プロジェクトを現実空間に可視化する!
~ スマホひとつで簡単にできるARの活用テクニック ~従来のプロジェクト説明や設計レビューでは、図面や模型を通じて「見る」ことが中心でした。 しかし、それだけでは関係者全員に同じイメージを共有するのが難しいという課題があります。
そこで注目されているのが、近年急速に普及してきた AR(拡張現実)技術 です。 ARを活用すれば、スマートフォンやタブレットを通して実寸大の建築や設備を「その場にあるかのように」体験できます。 モバイルアプリ 「DRA AR」 は、高価な機材や専門知識を必要とせず、手持ちのスマートフォンだけで、手軽にこの体験を実現します。
本講演では、実際の活用事例を交えながら「見る」から「体験する」へと変わる新しい形をご紹介します。
岸 航平 キシ コウヘイ
株式会社建築ピボット 開発部門
-
クロージング
千葉 貴史 株式会社建築ピボット 代表取締役社長
ネットワーキング
パーティー Reception Hall
本イベント終了後、17:20からネットワーキングパーティーを開催します。
フォーラムでの学びを深めつつ、業界のキーパーソンや登壇者と直接交流できる貴重な機会です。ビジネスの可能性を広げる場としてご活用ください。
どなた様でもご参加いただけます。
お時間ございましたら、お気軽にお立ち寄りください


