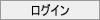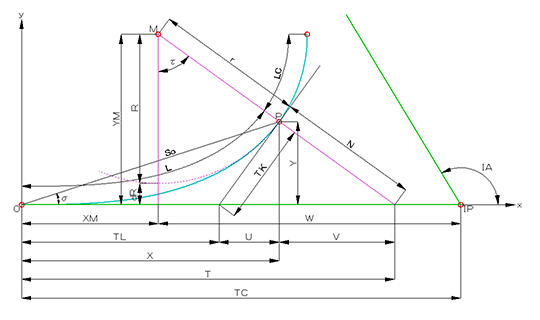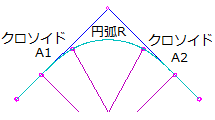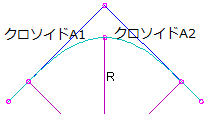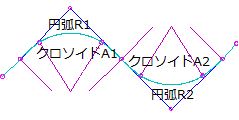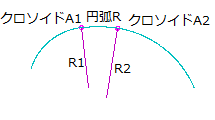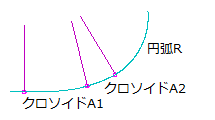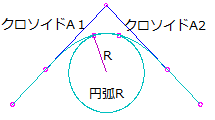コラムのページに戻る
クロソイドの雑学
◆
クロソイドの定義
◆
クロソイドは、R=曲線半径、L=曲線長とすると
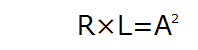
という式で定義され、このときのAをクロソイドパラメータと言います。
R、L、Aのうち2つがわかれば他の1つは簡単に求められます。
言いかえれば、R、L、Aのうちの2つを決めればクロソイド曲線を作図することができます。
※会員専用プログラムの
「AS-車の旋回軌跡コマンド」
では「RとL」によってクロソイド曲線を指定しています。
◆
クロソイドの要素と略号
◆
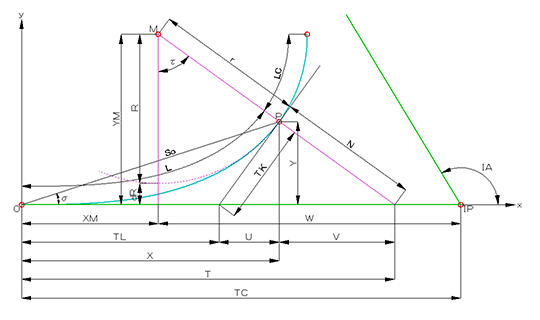
◆
略号説明
◆
|
略号
|
説明
|
略号
|
説明
|
略号
|
説明
|
|
IA
|
交角
|
YM
|
M点のY座標
|
N
|
法線長
|
|
R
|
内接円の半径
|
X
|
P点のX座標
|
T
|
X+V
|
|
A
|
クロソイドパラメーター
|
Y
|
P点のY座標
|
LC
|
円弧の長さ
|
|
L
|
クロソイド曲線長
|
σ
|
P点の極角
|
TC
|
0-IP間距離
|
|
τ
|
M点の接線角
|
So
|
動径
|
W
|
TC-W
|
|
dR
|
移動量(シフト)
|
TK
|
短接線長
|
|
|
|
XM
|
M点のX座標
|
TL
|
長接線長
|
|
|
◆
クロソイドの種類
◆
※上図の基本型や凸型にはクロソイドA1とA2の長さが違場合、「非対称基本型」「非対称凸型」となります。
◆
パラメータと半径の目安
◆
許容最大遠心加速度変化率から認めた許容最大パラメータおよび推奨値
|
|
高速道路の場合
|
道路構造令の条件
|
道路構造令の例外の条件
|
|
V
(km/h)
|
p=0.345m/sec3
|
p=0.6m/sec3
|
p=0.775m/sec3
|
|
A=1/4*√V3
|
推奨値
|
A=0.19*√V3
|
推奨値
|
A=1/4*√V3
|
推奨値
|
|
160
|
506
|
500
|
384
|
400
|
---
|
---
|
|
140
|
414
|
400
|
315
|
300
|
---
|
---
|
|
120
|
329
|
325
|
250
|
250
|
---
|
---
|
|
100
|
250
|
250
|
190
|
200
|
---
|
---
|
|
80
|
179
|
180
|
136
|
150
|
119
|
120
|
|
70
|
---
|
---
|
111
|
110
|
98
|
100
|
|
60
|
---
|
---
|
88
|
90
|
78
|
80
|
|
50
|
---
|
---
|
65
|
65
|
57
|
60
|
|
35
|
---
|
---
|
39
|
40
|
35
|
35
|
V:設計速度 p:遠心加速度の変化率 クロソイドポケットブック(*1)より
ドイツの経験法則によると基本型の場合、半径Rの1/3~1/1に入るパラメータのクロソイドを使うことが望ましいとされています。
また、設計速度に対して [1/4*√V3]以上のパラメータのクロソイドを使うことが視覚上望ましいとされています。
例えば、高速道路で設計速度100km/hを想定した場合、パラメータの推奨値は250です。
A≦R≦A×3を満たす半径Rは 250~750となります。
尚、以上の数値はあくまでも目安であり、実際の設計ではこの数値にこだわらなくても構いません。
(*1)クロソイドポケットブック:(社)日本道路公団 クロソイドポケットブック(改訂版)