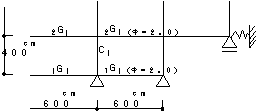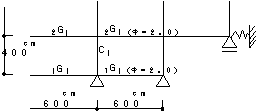俛倀俽亅俀丏俆丂俻仌俙廤
栚師
丂
Q.427
晹暘抧壓偑偁傞偲偒偵巟揰埵抲偺曄峏乮俛俴俛儗僐乕僪乯傪峴偄傑偡偑丄偙偺
応崌偵悈暯偽偹偼偳偺傛偆偵愝掕偟偨傜傛偄偱偡偐丠
丂
A.
儌僨儖壔偲偟偰偼堦斒偺巟揰偼墧捈丄悈暯偵偼崉丄夞揮偵偼帺桼乮僺儞乯偲側
偭偰偄傑偡偑丄埵抲傪曄峏偟偨巟揰偼悈暯曽岦偵傕帺桼乮儘乕儔乯偲側傝傑偡丅
晹暘抧壓偺堊偵埵抲傪曄峏偟偨婎慴偼抧斦偲愙偟偰偄傑偡偐傜幚嵺偼悈暯曽岦
偵帺桼偱偼側偔丄傓偟傠偁傞斖埻乮婎慴偲抧斦偲偺杸嶤掞峈偑偁傞乯傑偱偼崉
偺忬懺偵偁傝傑偡丅偟偐偟丄埵抲曄峏偟偨巟揰傪悈暯曽岦偵崉偲偡傞偲丄偦偺
憌偺憌偣傫抐椡偼慡偰巟揰偱晧扴偟丄拰偼慡偔悈暯椡傪晧扴偟側偔側傝傑偡丅
僐儞僋儕乕僩偺婎慴僼乕僠儞僌偲抧斦偲偺杸嶤學悢偼0.4乣0.5偺斖埻偲偄傢傟丄
埨慡棪偼1.5掱搙傪悇彠偝傟偰偄傑偡丅偟偨偑偭偰顟b偵嶌梡偡傞幉椡偺0.27
乣0.33攞偺悈暯椡偼崉偲偟偰偦偺婎慴偱晧扴偱偒傑偡偑偙偺抣傪挻偊傞偲婎慴
偼妸摦偡傞偙偲偵側傝崉偐傜帺桼偺忬懺偵曄傢傝傑偡丅拰偺晧扴悈暯椡偑側偔
偰偙偺忬懺偵側傞偺傪旔偗傞堊偵偼丄埵抲傪曄峏偟偨巟揰偵悈暯曽岦偺偽偹傪
愝偗晹暘抧壓偺拰傕揔愗側悈暯椡傪晧扴偡傞條偵偟側偗傟偽側傝傑偣傫丅
悈暯偽偹偺抣傪戝偒偔愝掕偡傞偲拰偺晧扴悈暯椡偼彫偝偔側傝丄悈暯偽偹傪彫
偝偔愝掕偡傞偲拰偺晧扴悈暯椡偼戝偒偔側傝傑偡丅
堦斒偵偼晹暘抧壓偺昗弨拰傪婎弨偵偟偰悈暯偽偹偺抣傪寛傔傞椺偑懡偄條偱偡丅
偡側傢偪昗弨拰偺墶椡暘晍學悢偵嫟捠偺扨埵12EK/(h*h)乲噑/(噋*噋)啎傪忔偠
偨傕偺傪偲傝傑偡丅僼儗乕儉拰偺嬋偘丄偣傫抐傪峫椂偟偨墶椡暘晍學悢偺寁嶼
偵偮偄偰偼寶抸妛夛偺俼俠婯弨晅14傪嶲徠偟偰壓偝偄丅
椺偲偟偰奒崅400噋丄昗弨拰偺抐柺60噋妏丄拰摢偵偮側偑傞偼傝偺抐柺40噋*80
噋丄拰媟偵偮側偑傞偼傝偺抐柺40噋*100噋偺応崌傪偟傔偟傑偡(恾427)丅
偙偺椺偱偼悈暯偽偹偺崉惈傪昗弨拰偲摨偠偲峫偊傟偽偦偺抣偼32倲乛噋偲側傝
傑偡丅
悈暯偽偹傪梌偊傞偙偲偵傛傝丄堏摦奺巟揰偼悈暯椡傪晧扴偟傑偡偑丄堏摦巟揰
埵抲偺婎慴偲搚偺杸嶤椡偑丄晧扴偟偨悈暯椡傛傝戝偒偄偙偲傪堦墳妋擣偟偰壓
偝偄丅
丂
丂
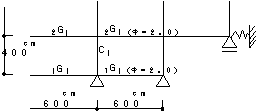
丂
俠丗60cm亊60cm
2俧1丗40cm亊80cm
1俧1丗40cm亊100cm
丂
俲O 亖 103
俲C 亖 2.7
俲2俧1 亖 5.6丂丂丂丂倎 亖 0.756
俲1俧1 亖 11.1
丂
俢 亖 倎丒倛C 亖 2.04
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂12俤俲
崉搙偺幚悢俢A乯亖 2.04 亊 丳丳丳丳丳 亖 32.13 亊103 噑乛噋
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂倛2
丂丂丂丂丂丂丂亖 32.13 t乛噋
丂
恾427
丂