2012年4月9日
DB6.0.4.7リリースノート
DB6.0.4.7の主な変更内容は以下の通りです。
変更内容の詳細は、BUS-5 Seriesのプルダウンメニューから[ヘルプ]→[ヘルプの目次]を選択し、「BUS-5 Seriesヘルプ」ページにある[DB6.4.0.7リリースノート]ボタンよりご覧ください。
 :BUS-5
:BUS-5  :DOC-RC/SRC
:DOC-RC/SRC
埋込み柱脚の基礎コンクリートの補強筋の検討 
側柱の埋込み柱脚に配置された補強筋の検討を行います。
鉄骨柱の側柱で、埋込み柱脚の補強筋のデータ入力がある場所の計算を行います。
補強筋は、上端・下端を同じとし、補強筋の被りは、基礎ばりの被りを用います。
(1) 降伏耐力
側柱の埋込み柱脚の降伏曲げ耐力
鋼構造接合部設計指針(2006年改定版)「7.4 埋込み柱脚の設計」を参考に、計算を行います。
| 荷重方向(a) | =上端補強筋が引張となる加力方向 =建物の外部の方向へせん断力が働く場合 |
| 荷重方向(b) | =下端補強筋が引張となる加力方向 =建物の内部の方向へせん断力が働く場合 |
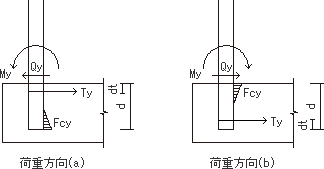
降伏耐力の検定
M
| M |
:埋め込み柱脚の降伏曲げ耐力(N・mm) |
| :鉄骨柱の降伏曲げモーメント(N・mm) |
(2) 終局耐力
側柱の埋込み柱脚の終局曲げ耐力
鋼構造接合部設計指針(2006年改定版)「7.4 埋込み柱脚の設計」を参考に、計算を行います。
| 荷重方向(a) | =上端補強筋が引張となる加力方向 =建物の外部の方向へせん断力が働く場合 |
| 荷重方向(b) | =下端補強筋が引張となる加力方向 =建物の内部の方向へせん断力が働く場合 |
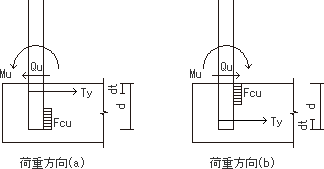
終局耐力の検定
M
| M |
:埋め込み柱脚の終局曲げ耐力(N・mm) |
| :鉄骨柱の終局曲げモーメント(N・mm) = 柱の終局時耐力(Ds時) (危険断面位置) |
下階壁抜け柱の検討方法の追加 
DB6.4.0.6までは、下階壁抜け柱の検討は地震時のα倍による検討出力を行っていましたが、
DB6.4.0.7より、下記の2通りの方法による算出方法を追加しました。
| ① | 主として「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化推進に係る耐震診断マニュアル」の内容による検討 |
| ② | 立体解析による鉛直荷重時と地震時の応力より、上部壁のせん断又は曲げ破壊時、引張柱の破壊時で、最小となる圧縮側の柱軸力による検討 |
2次診断の計算中に、環境設定で指定されているワークパスの「DOCOUT」フォルダに、①による検討結果「nowall1.csv」と②による検討結果「nowall2.csv」を出力します。
CSV形式のファイルで出力した検討結果は下記のプルダウンメニューから開くことができます。
(Microsoft ExcelなどCSV形式のファイルに対応したソフトが必要です。)
| (1) | DB6.4.0.6までの検討方法 |
| [耐震診断]→[CSV形式ファイルの出力]→[下階壁抜け柱の検討1] | |
| (2) | 「診断マニュアル」による検討方法 |
| [耐震診断]→[CSV形式ファイルの出力]→[下階壁抜け柱の検討2] | |
| (3) | 立体解析の結果による検討方法 |
| [耐震診断]→[CSV形式ファイルの出力]→[下階壁抜け柱の検討3] |
2009年版SRC診断基準による場合の変更点 
DB6.4.0.7より、SRC造の診断基準「2009年版SRC診断基準」と2次診断の計算方法「正負加力の平均」の組み合わせによる計算を行いません。
変更理由
DB6.4.0.6までは、SRC造建物の付加軸力の取り扱いは、「正負加力の平均」の指定の場合、常に圧縮側の変動軸力で計算を行っていました。(出典:1997年SRC耐震診断基準第1章総則P.53の記述)
このため、柱耐力が大きめに評価される場合がありました。
また、内法長さが、左右の腰壁、垂れ壁の配置の状況により異なる場合も、正負加力の平均の指定では、RC診断基準と同じ開口の内法高さにより計算を行っていましたので、正負加力の平均と正負加力別では結果が異なる状態でした。
これらを回避するためにDB6.4.0.7より変更しました。
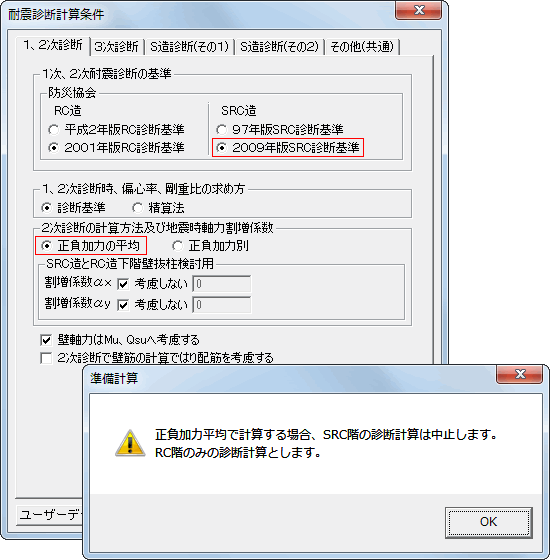
上記のように指定をし、RC造とSRC造の階がある建物の計算を実行するとメッセージを表示し、SRC階の診断計算を中止します。
また、すべての階がSRC造の場合は、診断階の指定が行われていないものとして扱います。
