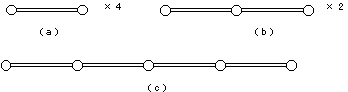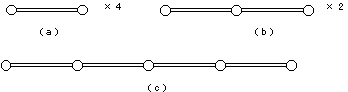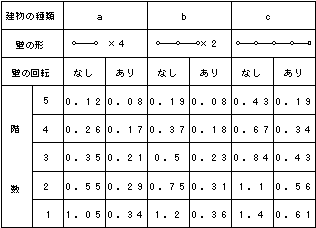�a�t�r�|�Q�D�T�@�p���`�W
�ڎ�
�@
Q.418
�t���[�������E�ϗ͕Ǖ����ɂ��ꂼ��ލ��悭�����͂S��������@�͂���
�܂����H
�@
A.
�ϗ͕ǂ͒��ɔ�ׂč������ɒ[�ɍ������߁A�����v�Z�ɂ��ꍇ�͉��͂��ϗ�
�ǂɏW�����邱�Ƃ͂������܂���B
���A�ϗ͕ǂ̌`��E���@��ς��Ȃ��Œ��A�ϗ͕ǂ����S���鐅���͂̕��S����
�ς���ɂ́A�ȉ��̓�̕��@���l�����܂��B
�@
�@
�@�̕��@
�@�ϗ͕ǂ̍��x���v�Z�������ɕt�ђ��̍��x��ϗ͕ǂ̕��S���鐅���͂�
�@�W���̒��̔C�Ӕ{�ɂȂ�悤�ɒ������܂��B�Ⴆ���E�ɕt�ђ������P�X
�@�p���̑ϗ͕ǂɕW������10�{���x�̐����͂S���������ꍇ�́A���E�̕t
�@�ђ��̍��x�����ꂼ��W�����̂T�{�Ƃ��܂��B�u���[�X�̒f�ʐς͑ϗ͕ǂ�
�@�F�������ŏ��l�i�Ⴆ�P�p2���x�j�Ƃ���̂��悢�ł��傤�i�e�f�j�A
�@�e�b�j�A�e�a�`���R�[�h�j�B�A���A���̏ꍇ�̑ϗ͕ǂ̒f�ʌv�Z�͒ʏ�̑�
�@�͕ǂ̏ꍇ�Ƃ͈قȂ�A�t�ђ��͈�ʒ��Ƃ��Čv�Z���A�ϗ͕ǂƂ��Ă͕ǔ�
�@�����ɂ��Čv�Z���܂��B���ɂ͕W�����̔C�Ӕ{��������f�͂���p���Ă�
�@��A�ǔɍ�p���Ă��邹��f�͔͂�r�I�����Ȓl�ƂȂ��Ă��܂��B�t�ђ�
�@�ƕǔ����ɍ�p���Ă��鐅���͂����v���A�ϗ͕ǂƂ��Ă̒f�ʌv�Z��ʂ�
�@�s���K�v������܂��B
�@
�A�̕��@
�@����w�ł̑ϗ͕ǂƒ��̕��S���鐅���͂������Â���ڈ��Ƃ��āA�ϗ͕ǂ�
�@���̉��͕��z�W���cW�A�cC�̔�Ƒϗ͕ǂ̍��x�C����������ђ��̕��S����
�@�����͂̊����̊W��\418�1�Ɏ����܂��B���̐����͕��S���͑ΐ��ڐ���
�@�Ȃ��Ă��܂��B
�@�\�̌�����
�@�@�@�cW�^�cC���P ����1.0 �̂Ƃ��@���̕��S����50��
�@�@�@�cW�^�cC���S ����1.0 �̂Ƃ��@���̕��S����20��
�@�@�@�cW�^�cC���S ����0.5 �Ȃ�� ���̕��S����33��
�@�ƂȂ�܂��B
�@����0.1�ɂ����Ƃ��Ă����̐����͕��S���̓���1.0�Ƃ�������0.1�{�Ƃ͂�
�@��Ȃ����Ƃɗ��ӂ��ĉ������B
�@���A�ϗ͕ǂ̉��͕��z�W���cC�A�cW�͂���f����������ΏۂƂ���Ύ�����
�@��苁�߂邱�Ƃ��ł��܂��B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@n �@12�d�E�h
�@�@�@�@�@�cC���� �P�P�P�P�P�P�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(a)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��3
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@m �f�E���E�
�@�@�@�@�@�cW���� �P�P�P�P�P�P�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(b)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁE��
�@
�@�@�@�@�@�@���F����w�ɂ����钌�̐��i�t�ђ��͊܂܂��j
�@�@�@�@�@�@���F����w�ɂ�����ϗ͕ǂ̐�
�@�@�@�@�@�@�d�F�R���N���[�g�̃����O�W��
�@�@�@�@�@�@�f�F�R���N���[�g�̂���f�e���W��
�@�@�@�@�@�@���F�K��
�@�@�@�@�@�@���F�nj�
�@�@�@�@�@�@�ȁF�ǂ̌`��W���i1.2�j
�@�@�@�@�@�@���F����f���x�C����
�@
�@���ۂ̌����̐v�ł͂cC�A�cW�͂���f�����̑��ɋȂ��A�������A�ꍇ�ɂ�
�@���Ă͉�]�Ȃǂ̍������l������܂��B�]���Ă��̕\�̊W�ɂ�钌�̐���
�@�͕��S���Ƃ͈قȂ��Ă��܂��B
�@�\ 418-2�͓��������ɓ����Ǘʂ����}418(a)�A(b)�A(c)�̌`��̑ϗ͕ǂ�
�@�z�u�������1.0�Ƃ��ĉ��͌v�Z�����Ƃ����ۂɊe�ϗ͕ǂƒ������S��������
�@�͂̕��S�W����i�j1���cW1�^�cC1�j���A �����A���Ōv�Z�����ϗ͕ǂƒ���
�@�����͕��S��i�j���cW�^�cC�j�̒l�ŏ��������l��\�������̂ł��B
�@�Ǎ��^�Ǖ��̒l���傫���ǁA�ꖇ�̕ǂł͏�w�ɂȂ�ɂ�āA��]���l��
�@���Ȃ��ꍇ���͍l�������ꍇ�̕������l�͏������ȂĂ��܂��B����f��
�@�������łcW�^�cC�����܂�Ƃ����ꍇ�͑S�Đ��l�� 1.0�ƂȂ锤�ł������
�@���I�ɂ́A���̗l�Ȏ��ӏ����ɂ���đϗ͕ǂ̍����͕ω����邱�Ƃ����߂�
�@�Ă��܂��B���l��1.0���Ă���ӏ��́A�ϗ͕ǂ̂���f�������㏸����
�@���̂ł͂Ȃ��A���̐����������������͂�S�������̕ω��ɂ���đ��ΓI��
�@�ቺ�������̂ƍl�����܂��B
�@����1.0�Ƃ��ĉ��͌v�Z�����ꍇ�ł��ϗ͕ǂ̂cW�͂��łɂ��̕ǂ̂�����
�@�f�����ɕ\418�2�̐��l�����Ƃ��ď悶���l�ɕω����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�\418�1��p�������w�肷�鎞�̎Q�l�ɂ��Ă��������B
�@
�@
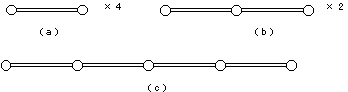
�@
�}418�@�ǂ̌`��
�@
�\418-1�@�ϗ͕ǂ̃��ƒ��̐����͕��S��
�@
�@
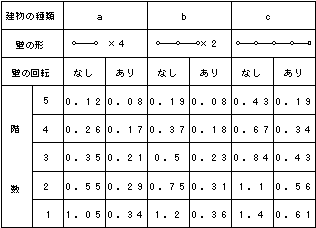
�@
�\418-2 �ϗ͕ǂ̐������S��̕ω��i�j1�^�j�j
�@
�j1�F�ϗ͕ǂɋȂ��A����f�i��]�j�������l�������Ƃ��̂cW�^�cc
�j �F�ϗ͕ǂɂ���f���x�݂̂��l�������Ƃ��̂cW�^�cc
�@